リベンジ退職とは
「退職時に必要なデータを削除して去る」「嫌みが込められたあいさつメールを送る」――。近年、こうした報復的な行動を伴う辞め方が「リベンジ退職」と呼ばれ、注目を集めています。
経営コンサルタント会社「スコラ・コンサルト」が行った調査によると、全国2106人を対象にしたアンケートで 約1割(11.8%)がリベンジ退職を経験した と回答しました。
最も多かった困りごとは「退職者の仕事を分担することになり、職場が大変になった」(29.0%)。しかしそれ以上に深刻なのは、データ消去や内部情報暴露といった悪質な行為です。
実際にあったリベンジ退職の事例
- 部下が退職時にPCのデータをすべて消去し、メモリを抜き取っていた
- 書類をばらまいて退職し、引き継ぎが混乱
- ハラスメントをでっち上げて訴える
- 皮肉たっぷりのあいさつメールを送信
こうした行為は職場に大きな混乱をもたらし、残された社員の負担を急増させます。
なぜリベンジ退職が起きるのか
背景には、仕事内容への不満や人事評価への不信感、上司・同僚との関係性の悪化があります。
- 思っていた仕事内容と実際が違う
- 苦手な業務を任され続ける
- 公平に扱われていないと感じる
- 人間関係のトラブルが解決されない
これらが積み重なり、最後に「爆発」してしまうのがリベンジ退職です。
キャリアへのリスク
一時的に気持ちは晴れるかもしれませんが、報復行為は その後のキャリアにマイナス影響を及ぼす可能性が高い と指摘されています。前職の噂が広まり、転職先で不利に働くことも十分あり得ます。
また、日本でも悪質な行為は損害賠償や懲戒の対象になるケースがあります。
欧米で起きた派手な事例
2010年、米航空会社の客室乗務員が乗客に腹を立て、緊急脱出スライドを展開して降機。器物損壊の罪で逮捕され、会社に約147万円を支払う判決が下りました。派手な「リベンジ退職」は話題になりますが、結末は決して明るくありません。
まとめ:立つ鳥跡を濁さず
退職は新しいキャリアの第一歩です。残された同僚や職場に迷惑をかける「リベンジ退職」は、結果的に自分に返ってきます。
日本には「立つ鳥跡を濁さず」ということわざがあります。きれいに退職することが、自分の評価や人間関係を守り、次のキャリアの追い風になるのではないでしょうか。
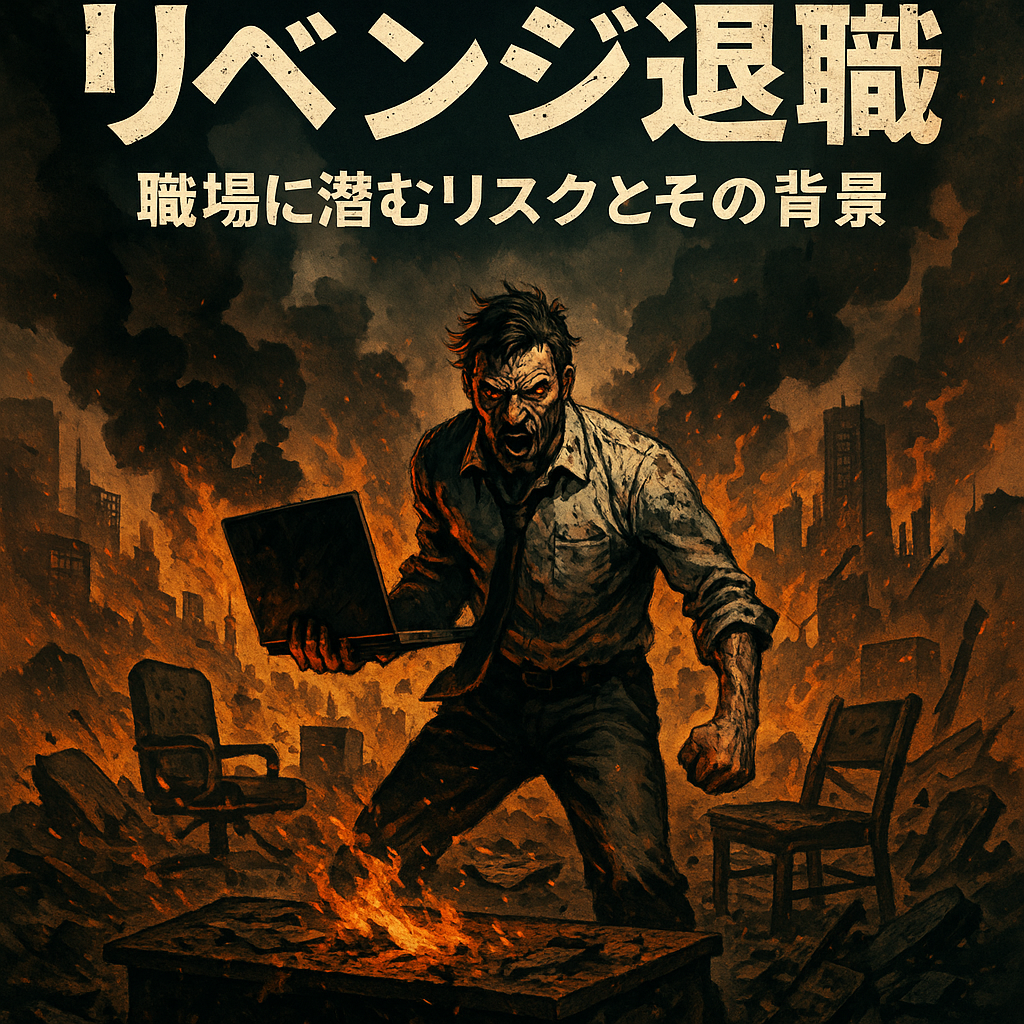

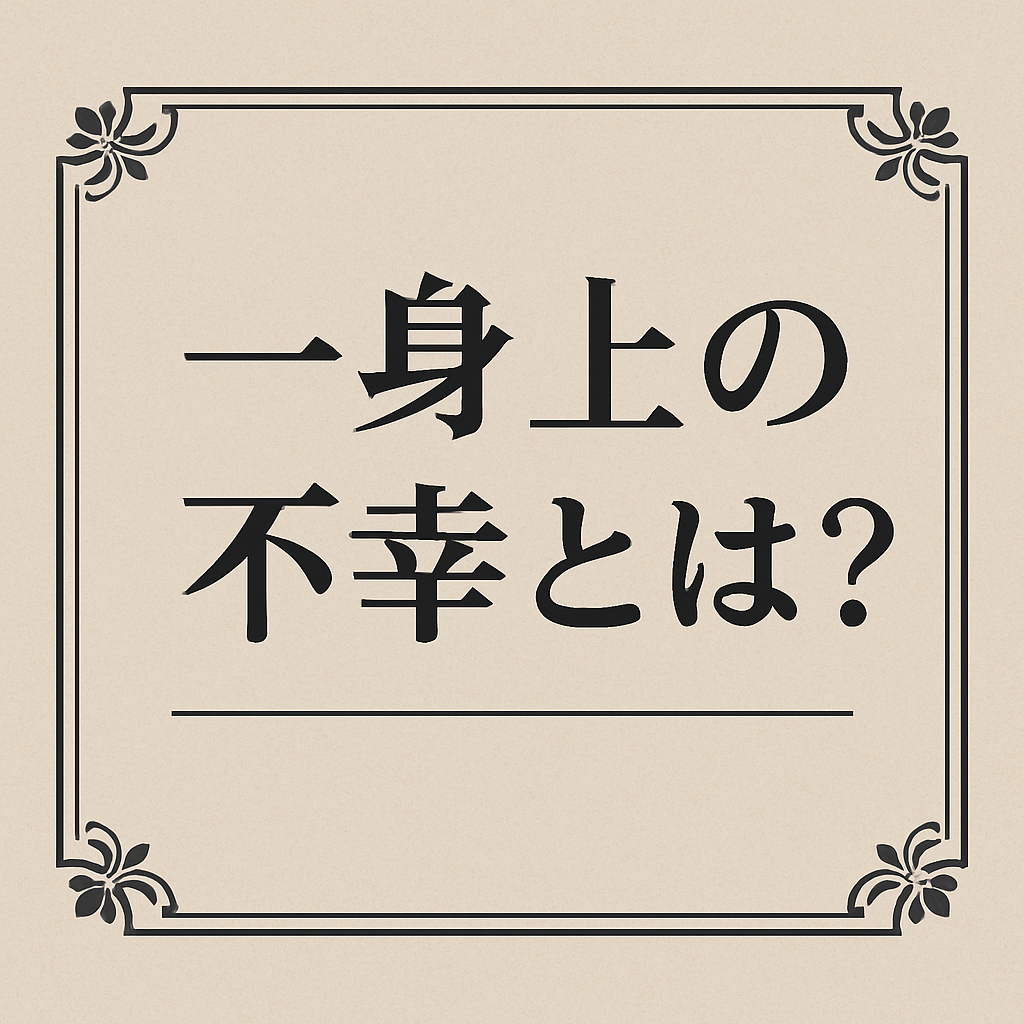
コメント