「え、これ、日本製じゃなかったの⁉」
そんな声が、今、世界中で聞こえてきます。
精密な品質管理と高い信頼性で知られる日本製品。しかしそのブランド力を逆手にとった“模倣品”が、今や海外のECサイトに氾濫しています。被害は大手メーカーだけではなく、地方の中小企業にまで広がっており、見過ごせない社会問題となりつつあります。
今回は、実際の事例をもとに、なぜニセ日本製品が増えているのか、そのリスクや対策、そして私たち消費者ができることまで、わかりやすく解説します。
レバノンでの爆発事件に「日本製」の影?
2024年9月、中東・レバノンで起きた爆破事件では、日本の通信機器メーカー「アイコム」の模倣品が関与していた可能性が浮上しました。
報道によれば、親イラン武装組織ヒズボラの戦闘員が使用していたトランシーバーが相次いで爆発し、多くの死傷者が出たとのこと。その機器には「ICOM」のロゴが確認されましたが、実際には10年以上前に販売終了したモデルであり、海外で流通していた模倣品と断定されました。
アイコム社は緊急対策チームを立ち上げ、各国のECサイト上にある約4,500件の出品を削除。しかし模倣品は正規品とほぼ同じ見た目で、消費者でも判別が困難。さらに削除しても、時間が経てばまた別の出品者が現れるという“いたちごっこ”が続いています。
ミラブル、スイッチのコントローラー…模倣品のターゲットは多種多様
被害はアイコム社だけではありません。高機能シャワーヘッド「ミラブル」で知られるサイエンス社(大阪市)も、模倣品の被害を受けています。
購入者から「水が出ない」などの苦情が相次ぎ、調査したところ外見はほぼ同じだが、部品の素材や内部構造が明らかに異なる製品が見つかりました。輸入差し止めは4,000件にものぼり、日本の税関も水際対策に奔走しています。
また、「Nintendo Switch」のコントローラーや化粧品、自転車部品など、模倣品のジャンルは多岐にわたります。
主な供給元はやはり中国、そして香港・トルコも
経済協力開発機構(OECD)の報告によると、世界の模倣品の54%は中国から、22%は香港、12%はトルコから供給されているとされています。2024年には日本の税関が差し止めた知的財産侵害品は過去最多の33,019件にのぼり、そのうち実に8割が中国からのものでした。
模倣品の多くは、外見は精巧に作られていても中身は粗悪品。安全性に重大な問題を抱えていることも多く、製品としても信頼性がありません。
韓国の対策は一歩先を行く
隣国・韓国では、「Kブランド」の保護に国全体で取り組んでいます。
韓国特許庁は、商標権侵害を取り締まる特別司法警察を設置。AIを活用した監視体制や、114か国のECサイトでの模倣品チェックなど、具体的かつ大規模な対策が進んでいます。
さらには、官民連携で「Kブランド保護官民協議会」を立ち上げ、中国や東南アジアでの法的対応支援体制も整備。こうした動きは、模倣品被害の抑止に一定の効果を上げています。
日本はどうする?中小企業の対応が急務
日本では、まだ十分な模倣品対策が進んでいるとは言えません。
特に中小企業は人材・予算ともに限られており、海外の模倣品を監視・対処する体制を持てないのが現状です。
ECサイト側に模倣品の迅速な削除を義務づける制度や、悪質な出品者の利用制限など、国際的なルールづくりが急務となっています。
賢い消費者になるために
私たち消費者も「安いから」「レビューが良いから」だけで商品を選ぶのではなく、次のような視点を持つことが大切です。
- 販売者の情報を確認する(正規代理店かどうか)
- レビューが極端に偏っていないかをチェック
- 公式サイトでの価格や見た目と比較する
- 明らかに安すぎる場合は警戒する
「見分けがつかないなら買わない」という選択も、模倣品の流通を防ぐ一歩になります。
まとめ:模倣品問題は“他人事”ではない
日本の技術や信頼は、世界中で高く評価されています。だからこそ、ニセモノも出回るのです。
しかしその陰で、メーカーの損失、安全性のリスク、ブランドイメージの低下といった深刻な問題が生まれています。
企業・政府・そして私たち消費者一人ひとりが、「本物を見抜く目」を持ち、模倣品問題に対して“見て見ぬふり”をしないことが、未来の日本ブランドを守ることにつながるのです。


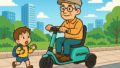
コメント