日本の伝統文化の中には、華やかさと静かな緊張感が共存する遊びがあります。その一つが**「投扇興(とうせんきょう)」**です。
桐の台に立てられた「蝶」と呼ばれる的に向かって扇を投げ、落ちた形で得点を競うこの遊びは、江戸時代から続く風雅な対戦型ゲーム。
今回は、その歴史やルール、使う道具、現代での楽しみ方まで、詳しくご紹介します。
投扇興の歴史と由来
投扇興が誕生したのは江戸時代中期・安永二年(1773年)ごろの京都と言われています。
当時、中国から伝わった「投壺(とうこ)」という遊びがありましたが、作法やルールが複雑で、誰でも気軽に楽しめるものではありませんでした。
そこで、女性や子どもでも遊べるようにと考案されたのが投扇興です。庶民の間でたちまち人気となり、宴席や花街などでも親しまれました。
しかし一方で、賭け事に利用されることもあり、幕府から禁止令が出された時期もあります。
明治時代に入ると西洋文化の影響で次第に衰退し、ごく一部の愛好家の間で細々と続けられるようになりました。
戦後になると復興の動きが進み、現在では全国各地に大小さまざまな流派や団体が存在します。テレビや新聞でも取り上げられ、再び注目されるようになっています。
投扇興に使う道具
投扇興は、以下の3つの道具で構成されます。
1. 蝶(的)
- イチョウの葉の形をした布張りの的
- 両脇に鈴が下がり、下部には重り(五円玉など)
- 一般的なサイズは約9×9cm
流派によっては木製や和紙製、あるいは小銭を包んだ「花」と呼ばれる的を使用することもあります。
2. 枕(台)
- 蝶を乗せる台
- 桐材が一般的で、絵や文字、友禅紙で装飾されることも
- 標準サイズは17.5×9×9cmほど
3. 扇
- 投扇興専用に作られた軽量の扇
- 骨の数や大きさは流派によって異なり、ふわりと飛ぶように工夫されています
例:其扇流は骨8本、御扇流や戸羽流では骨10~12本など
得点の付け方とルール
投扇興では、扇を投げて「蝶」や「枕」と作る形を、源氏物語や百人一首になぞらえた名前と点数で評価します。
例えば、扇が蝶を完全に倒すと高得点、枕と蝶の間に特定の角度で止まれば別の点数…というように、形の美しさや難易度によって得点が変わります。
この「形を読む」過程が、ただのゲームを超えて雅な知的遊びにしているポイントです。
流派と団体
有名な流派は以下の4つです。
- 其扇流(きせんりゅう)
- 御扇流(みせんりゅう)
- 都御流(みやこおんりゅう)
- 戸羽流(とわりゅう)
その他にも数十もの団体が存在し、それぞれが独自のルールや採点法を持っています。
流派によっては扇の重さや蝶の形が異なり、プレイの感覚も変わるため、複数の流派を体験してみるのも面白いでしょう。
現代での楽しみ方
近年は、京都や東京の老舗旅館、和文化体験施設などで、初心者向けの投扇興体験ができます。
また、地域の文化祭や国際交流イベントでも紹介されることが多く、外国人観光客にも人気です。
さらに、投扇興は年齢や体力を問わず遊べるため、親子や三世代で楽しめる伝統ゲームとしても注目されています。
まとめ
投扇興は、江戸時代に生まれ、現代に蘇った日本の美しい遊びです。
扇を投げる一瞬の静と動、形の妙、雅な得点名…。
一度体験すれば、その奥深さに引き込まれること間違いなし。
私自身も、いつか京都の老舗で投扇興を体験し、その世界観を肌で感じてみたいと思っています。

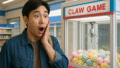
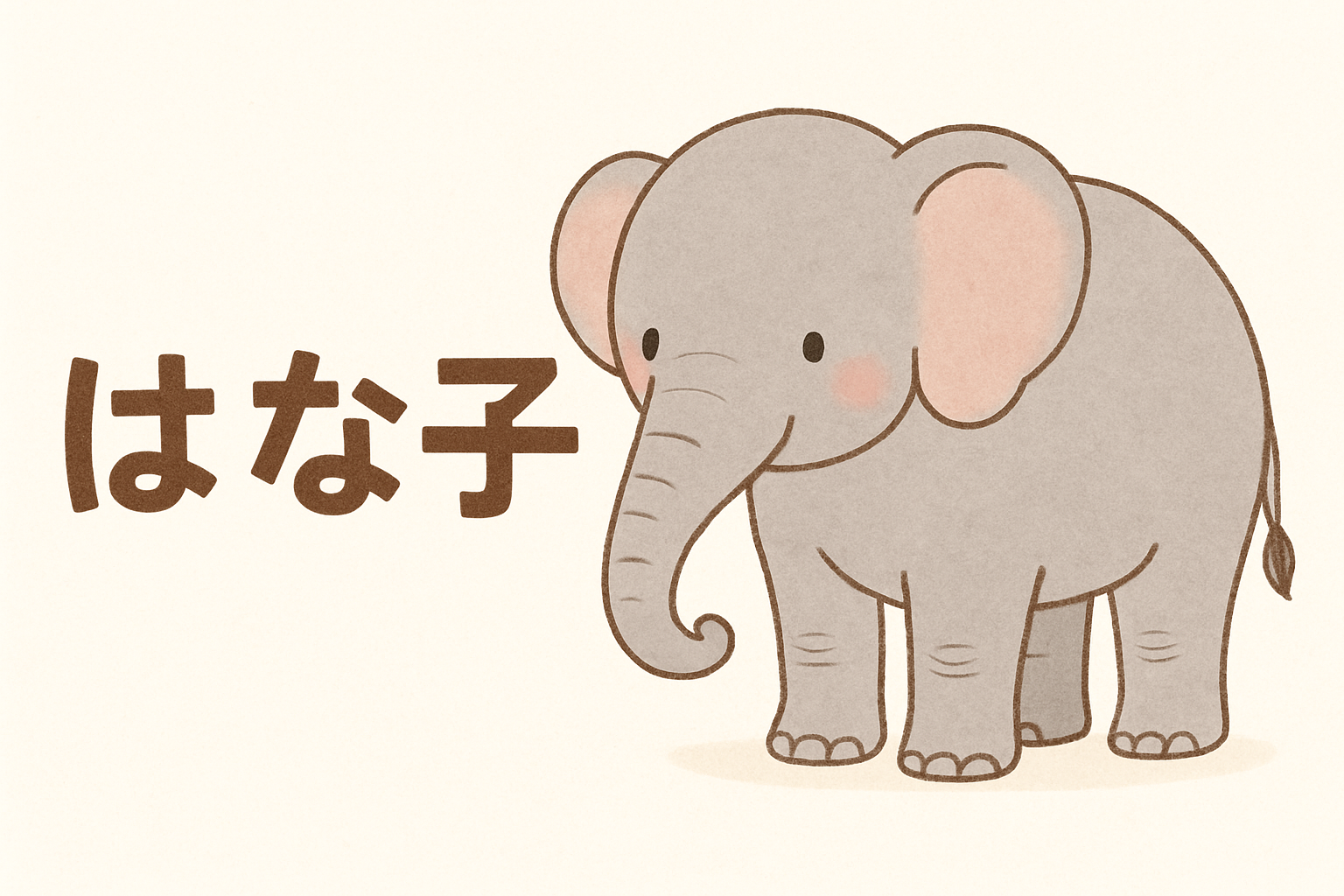
コメント