「PayPay、楽天ペイ、メルペイ、Apple Pay、〇〇ペイ…」
スマホの中が決済アプリだらけ、という人は少なくないでしょう。
キャッシュレス化は便利なはずなのに、日本ではなぜか使いにくく感じる。実際、現金で払ったほうが早い場面もあります。
この記事では、日本のキャッシュレスが複雑な理由と、改善に向けたヒントを考えてみます。
店側の本音:「コストは見えやすく、メリットは見えにくい」
キャッシュレス決済を導入するには、機械の購入やスタッフの教育といった“導入コスト”がかかります。
さらに、これまで無料だった決済手数料が発生するようになり、小規模店舗ほど負担が大きくなります。
一方でメリットは、「両替の手間が減る」「レジ締めが簡単になる」といったものですが、これは時間的コストのため“お金として見えにくい”のです。
その結果、店舗側は「やっても得にならない」と感じやすくなります。
海外の成功事例:シンガポールの統一QRコード
キャッシュレスがうまく進んでいる国は「統一性」を重視しています。
例えばシンガポールでは、数十社の決済サービスが存在しますが、QRコードは1種類に統一。
お店も利用者も「どのQRコードを使えばいいか迷う」ことがなく、非常にスムーズです。
日本の課題:複雑さと待ち時間
日本のキャッシュレス決済はこうです。
- 「何ペイで払いますか?」と聞かれる
- 店側スキャン方式と客側スキャン方式が混在
- さらに「ポイントカードはお持ちですか?」と聞かれる
支払いが完了するまで複数のアプリを立ち上げる必要があり、むしろ時間がかかります。
本来「お客様を待たせない」ことが強みのはずなのに、現金の方が速いという逆転現象が起きています。
日本はキャッシュレス向きの国?
それでも、日本はキャッシュレスと相性が良いとも言えます。
- 1円単位まで価格を設定する文化(例:998円)
- 硬貨が多く、お釣りの準備に手間がかかる
ヨーロッパでは小銭を廃止する動きが進み、「ラウンディング(切り上げ・切り捨て)」が導入されつつあります。
キャッシュレスなら端数をそのまま扱えるため、日本の細かい価格設定には非常にマッチしています。
現金も必要不可欠
「キャッシュレスが便利だから現金は不要」という考え方には注意が必要です。
視覚障害者や高齢者など、キャッシュレス利用が難しい人にとっては現金が生命線。
すべての人が買い物をする以上、決済手段は“ユニバーサル”でなければなりません。
現金を完全に排除するのではなく、現金を維持するためにキャッシュレスを進めることが大切です。
筆者の提案:決済アプリの一本化を
私が理想だと思うのは、決済アプリを一つに限定し、そのアプリから複数のカードや銀行口座を選んで引き落とせる仕組みです。
これなら利用者もお店も迷わずに済みますが、残念ながら各社の利権が絡んでいるのが現状でしょう。
まとめ:自治体と国のサポートがカギ
- 店舗にとっては「導入コスト>見えにくいメリット」になりがち
- 日本はキャッシュレス向きの土壌がある
- 現金は残すべきであり、両立が必要
そのためには、自治体が端末を貸し出したり、利用方法をサポートする仕組みが重要です。
国も「キャッシュレス決済比率〇%」という数字目標だけでなく、現場に寄り添った支援を進めるべきです。
複雑すぎる日本のキャッシュレス。
シンプルで誰もが使いやすい仕組みを整えることが、次の大きな課題なのではないでしょうか。

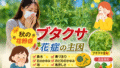

コメント